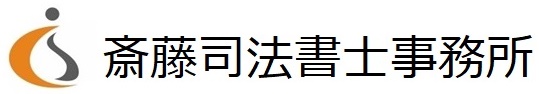01建物を新築したらする不動産登記とは?
表示に関する登記では、不動産の物理的状況が記録されます。
例えば、建物がどの場所にあるのか、居宅なのか店舗なのか、木造なのか鉄筋コンクリート造なのか、広さはどのくらいなのかといったことが記録されます。
権利に関する登記では、不動産の権利関係が記録されます。例えば、不動産を誰が所有しているのか、担保権は設定されているのかといったことが記録されます。
表示に関する登記で最初にするのが「表題登記」、権利に関する登記で最初にするのが「保存登記」です。
◇ 表題登記とは?
建物を新築したらまず最初にする登記のことで、建物の物理的な状況等が登記されます。
一般的な建物表題登記の登記事項
- 所在・家屋番号・種類・構造・床面積
- 所有者の住所・氏名
表題登記は申請義務あり
表題登記は法律で義務付けられており、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています(不動産登記法47条)。また、法律上は、表題登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになっています(不動産登記法164条)。
専門家は土地家屋調査士
表題登記は自分で申請することも可能ですが、専門家に依頼する場合は、表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士に依頼することになります。
当事務所ではワンストップで土地家屋調査士への依頼も行っています。
◇ 保存登記とは?
表題登記の次にする登記のことで、権利(所有権)に関する最初の登記になります。
一般的な建物の保存登記の登記事項
- 所有者の住所・氏名
家の新築時の名義は、所有権保存登記の所有者の欄に記載されている内容(住所氏名)のことを言います。
保存登記は権利の登記の出発点
権利に関する登記をするには、その前提として保存登記がされていなければなりません。
権利に関する登記には、売買による所有権移転やローンを組んだときの抵当権設定などがあります。例えば、建物の売った場合、表題登記だけしていて保存登記をしていない売主は、保存登記をしなければ、買主へ所有権移転登記をすることができません。また、ローンを組むときも、保存登記をしなければ、抵当権設定登記をすることができません。
保存登記は登記義務なし
保存登記を含む権利に関する登記は、表題登記とは異なり、その申請が法律で義務付けられていません。
売買や抵当権設定など不動産に関する権利の変動は、その登記することによって、その権利の変動を第三者に対して主張することができるようになります。このような利益を受けるかどうかは当事者の意思に委ねればよいという考え方から、権利に関する登記を申請するかどうかは任意となっています。
専門家は司法書士(当事務所になります。)
保存登記は自分で申請することも可能ですが、専門家に依頼する場合は、権利に関する登記の専門家である司法書士に依頼することになります。
専門家に依頼しないで、自分で手続きを誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ表題登記、保存登記ともにご自身で手続きすることは可能です。事案によっては手続きが難しい場合もあります。
住宅ローンなどを組まれる場合は、ご自宅への担保(抵当権)の設定が同時に必要になりますので、銀行がご自身での登記を認めないことも考えられます。