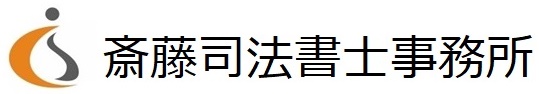01相続人がいない場合
被相続人に法定相続人がいない場合、遺言書も残されていなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。
そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属することになります(つまり、国のものになります)。
02相続人不存在の場合の手続きの流れ
1. 家庭裁判所に対する相続財産管理人選任の申立(民法952条1項)
利害関係人または検察官が、被相続人の相続開始他の家庭裁判所に申立をします。
![]()
2. 相続財産管理人選任の公告(民法952条2項)
この広告は、管理人選任を公示することのほか、第1回目の相続人の捜索の意味を持ちます。広告期間は2か月です。
![]()
3. 相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告(民法957条1項)
相続財産管理人選任公告の官報掲載日から2か月を経過しても相続人が現れない場合には、2か月以上の期間を定めて、相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告をします。
![]()
4. 相続人捜索の公告(民法958条)
家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求により、6か月以上の期間を定めて捜索の公告を行います。3回目の相続人の捜索の公告であり、相続人の不存在を確定させる公告です。
![]()
5. 特別縁故者への財産分与の申立
財産分与を求める者から被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。この申立は、上記相続人捜索の公告(民法958条)の期間満了の翌日から3か月以内にする必要があります。
![]()
6. 分与の審判もしくは申立却下の審判
家庭裁判所が、縁故関係の内容や程度などの一切の事情を総合的に調査し、分与もしくは申立却下の審判をします。
![]()
7. 特別縁故者に対する分与財産の引渡し
分与の審判が確定すると、相続財産管理人は特別縁故者に対して遅滞なく財産を引き渡します。
![]()
8. 残余財産の国庫への引継ぎ
別縁故者からの財産分与の申立がないまま、相続人捜索の公告期間満了時から3か月が経過したとき(または分与の申立が却下されたとき)には、相続財産は国庫に帰属します。
![]()
9. 管理事務終了
管理人は、管理終了報告書を、家庭裁判所に提出します。
03不動産の共有者と特別縁故者のどちらが優先されるか
民法255条には、次のように規定されています。「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」。
そうしますと、相続人不存在の場合特別縁故者への財産分与の手続きと、不動産の共有者への帰属のどちらが優先されるのかという問題が生じます。民法255条だけを読むと、相続人のいない被相続人残した財産が共有の不動産のみであった場合には、他の共有者がその持分を引き継ぐことになり、相続財産管理人の選任の必要はないようにも思えます。
しかし、この点について最高裁で争われた結果、最高裁の判断では、特別縁故者への財産分与の方が、民法255条の規定に優先するということになりました(最高裁判所 平成元年11月24日 判決)
したがって、
① まずは相続債権者や受遺者に対する清算手続を行う。
その後、
② 民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与を検討。
特別縁故者に該当する者がいない場合に、
③ 民法255条による共有者への帰属。
このような順番となるということになります。